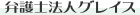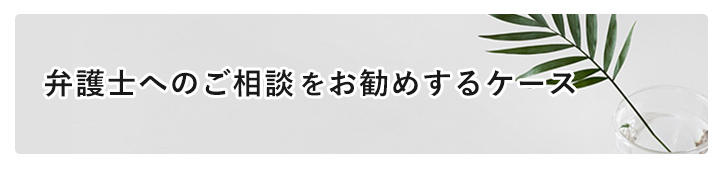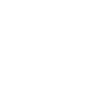離婚届けを提出する前に確認すべきこと
目次
離婚時に確認すること
1.はじめに
離婚届は、双方の合意で作成・提出することができます。お子様がいらっしゃる夫婦の場合、親権だけは決めなければいけませんが、養育費、面会交流、財産分与、年金分割については必ずしも決める必要がありません。
離婚が成立してしまうと、改めて相手と条件の協議を進めるのは簡単ではありません。また内容によっては、時効等の経過によって後から請求ができなくなってしまうものもあります。
離婚の合意が整っていたとしても、他に確認すべきことがないかしっかりと確認しておきましょう。
2.具体的な確認事項
(1) 養育費
一般的に、夫婦の収入とお子様の人数・年齢によって定まります。離婚後に協議をすることも可能ですが、協議が整うまでタイムラグが生じかねません。もちろん、後から未払い分を請求できる場合もありますが、養育費はお子様の健やかな成長に必須の費用です。可能な限り事前に確定し、タイムラグが生じないようにしましょう。
(2) 面会交流
「離婚をした途端に子供に会わせてもらえなくなった」というご相談を頻繁に受けます。場合によっては、「子供に会わせてもらえないどころか行方も分からない」という方もいらっしゃいます。
面会交流は性質上どうしても抽象的な決め方しかできませんが、それでも大体の頻度(月1回等)や連絡の取り方、住所変更の際の通知義務等についても合わせて定めておくことをお勧めします。
(3) 財産分与
財産分与は、「離婚の時から二年」以内に請求をしなければ権利を失ってしまいます(民法第768条第2項但書)。2年という月日は意外とあっという間に過ぎてしまいます。可能な限り離婚と同時に財産分与の取り決めをしておくことをお勧めいたします。
(4) 慰謝料
いわゆる離婚慰謝料であれば、「離婚が成立した時」から「3年」以内に請求をしなければ権利を失ってしまいます(民法第724条、最高裁判例昭和46年7月23日判決)。財産分与の「2年」よりは若干長いですが、やはり可能な限り離婚と同時に取り決めをしておくことをお勧めいたします。
(5) 年金分割
財産分与同様、「離婚の時から2年」以内に請求をしなければ権利を失ってしまいます。財産分与同様、可能な限り離婚と同時に取り決めをしておくことをお勧めいたします。
3.最後に
離婚協議の多くは離婚そのものより離婚条件で紛争になることが殆どです。可能な限り後の紛争を回避できるよう、離婚届けを提出する前に協議できる内容はしっかりと取り決めをしておきましょう。
離婚に伴う具体的な確認事項にご不安を覚えた方は一度当事務所にご相談下さい。
お金について
-

不貞慰謝料を請求したい
不貞行為とは、婚姻しているものが婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことです。これについては、不貞行為があれば、ただちに離婚事由になるという考えと、不貞行為があり、その結果、婚姻関係が破たんしたときに、不貞行為が離婚原因になるという考えの二つがあります。 裁判所は、不貞行為があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚を認めないことができるので、結果的には、どちらの考えでも同じと思われますが、実務では、裁判所が民法770条2項によって離婚請求を棄却する判決をすることはほとんどありません。 また、不貞行為は、相手の意思の有無は関係ありません。相手方と合意がある(例えば不倫行為や売春行為)も、合意がない場合(例えば強姦)であっても、不貞行為になります。一時的なものか、継続的なものかも問いません。 なお、同性との性的関係は、不貞行為には当たりませんが、民法770条1項5号に規定される「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる場合があります。 他方の配偶者が相手方の不貞行為を知ったうえで、これを許したような場合(これを宥恕といいます)には、離婚原因としての不貞行為にはならないと考えられています。 不貞行為の立証は、非常に困難です。なぜなら、不貞の現場は密室である場合が多いためです。不貞現場の写真・ビデオや動画撮影等がない場合には、相手が認めない場合、立証は難しいでしょう。場合によっては、探偵を雇い、証拠を集めることも検討する必要があるかもしれません。 メールやラインの内容等で密接な交際をしていることが明らかになることがありますが、これだけでは性的関係をもったと100%いえるかというと、そうではありません。もっとも、このような場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ますので、証拠として保全しておく必要があります。 不貞行為は、離婚事由となるだけではなく、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害したことになりますので、不法行為に基づく損害賠償義務が発生します。 この場合不貞行為の相手方も、不貞行為をした配偶者と共同して不法行為を行ったことになりますので、同じく共同して損害賠償義務を負います。 なお、不貞行為されていたとしても、その時点においてすでに婚姻関係が破たんしていたような場合には、婚姻共同生活の平和を破壊したとは言えませんので、損害賠償義務も生じません。これは、不貞をした相手方が必ずと言っていいほど反論してくる事情ですので、婚姻関係の破たんの有無は重要な争点となります。 不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。 不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。 一般的に70万円~250万円といわれておりますが、あくまでもケースバイケースです。 ただし、不貞の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。なぜなら、不貞判明後、夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に至った場合とで慰謝料が同額では不公平な結論となるためです。 例えば、慰謝料として100万円が相当であるとするならば、不貞行為をした配偶者と、不貞相手と、両者に対して100万円ずつ、合計200万円を請求できるわけではありません。 不貞行為をした配偶者と、その不貞相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから、1つの不法行為と評価され、慰謝料は総額で100万円となります。このため、例えば離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額受け取った場合には、不貞相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。 また、慰謝料請求権は、不貞行為それ自体を理由とする場合には、不貞行為があったこと等を知った時から3年、不貞行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年で時効となり、慰謝料の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。 夫・妻が浮気しているかもしれない、という場合、弁護士に相談することによって、情報収集の方法や、離婚のタイミング等、様々な情報を得ることができます。また、弁護士に依頼すれば、不貞相手や離婚したい相手と直接やりとりをせずにすむため、精神的負担も大幅に軽減することができます。 その結果、通常よりスムーズに離婚をすることができたり、損害賠償を請求できたりする可能性が高まります。少しでも不安な場合、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 「慰謝料」に関するQ&A よくあるご質問のうち、慰謝料に関するご質問をまとめました。 「浮気・不倫をされた方で、慰謝料が争点」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、浮気・不倫をされた方で、慰謝料が争点であった事例をまとめました。 [myphp file='link-money']
-

不貞慰謝料を請求された
配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。 相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。 弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。 裁判で認められる慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、現実には、70万円から250万円が多く、500万円を超えることは少ないと言われています。 また、不貞をした配偶者の責任と不貞の相手方の責任は、共同不法行為となるため、慰謝料は連帯債務となり、不貞をされた配偶者はその双方に慰謝料請求をできます。 不貞をした配偶者Aさんと、不貞の相手方Bさん、不貞をされた配偶者のCさんがいるとすると、AさんとBさんは、共同してCさんに不法行為である不貞行為を行っているということになります。ですから、CさんはAさんとBさん双方に慰謝料請求をできるのです。 たとえば、Cさんが不貞によって受けた心の痛みを慰謝するためには200万円かかるとします。そしてAさんとBさんが100万円ずつの責任があるとします。この場合、共同不法行為は不真正連帯債務ですから、Aさんに100万円とBさんに100万円請求してもよく、Aさんに200万円全額の請求を行っても、Bさんに200万円全額の請求を行っても問題ありません。これが連帯債務です。 相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう示談書を作っておくのがよいでしょう。 夫婦関係が既に破綻しているような状態で不貞行為がされた場合は、慰謝料請求は認められません。 また、不貞行為の相手方に慰謝料請求をする場合は、不貞行為に至る過程において、不貞行為の相手方に特別の事情がある場合、例えば、相手の女性が夫が結婚していることを知らなかった、または、夫が相手の女性に対してしつこく関係を迫った等の事情がある場合には、慰謝料請求が認められなかったり、認められたとしても非常に低額になる可能性もあります。 また、慰謝料請求権は、不貞行為それ自体を理由とする場合には、不貞行為があったこと等を知った時から3年、不貞行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年で時効となり、慰謝料の請求ができなくなりますので、その場合は、時効を援用すれば、慰謝料を支払う必要はなくなります。 慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。 ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。 ①配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている、②請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい、③不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている 等でお悩みの方は、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 「慰謝料」に関するQ&A よくあるご質問のうち、慰謝料に関するご質問をまとめました。 「浮気・不倫をした方で、慰謝料が争点」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、浮気・不倫をした方で、慰謝料が争点であった事例をまとめました。 [myphp file='link-money']
-

財産分与
夫婦の財産はどうやって分けるでしょか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合や、話合いすらしたくないという場合には、十分な話合いをせずに離婚してしまう場合も多々見られます。 しかし、特に離婚後の生活に不安がある場合には、離婚後に経済的に困窮しないよう経済面での清算もきちんと行いましょう。 離婚する際に、婚姻期間中に形成された財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分配することです。 婚姻関係破綻の原因が相手にないと請求できない慰謝料と違い、財産分与の請求は、自分に離婚の原因があった場合であっても請求できます。 不動産の財産分与についてはこちらもご覧ください。 不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。 財産分与の対象となる財産(夫婦共有財産)としては、結婚後の夫婦の収入を原資とする預貯金、不動産、車などがあります。 親から相続や贈与を原資とする預貯金、不動産、婚姻前から持っていた預貯金、不動産等は、いわゆる特有財産といわれる、財産分与の対象にならない財産です。 と、言葉で説明するのは簡単なのですが、実際は、この共有財産、特有財産の振り分けは、家庭裁判所の調停や訴訟で熾烈な争いになることが最も多いポイントの一つです。人間として、離婚する配偶者に自分名義の財産の半分を持っていかれたくはない、というのは自然な心情ということなのだと思われます。 この共有財産と特有財産の振り分けについては、法的にもなかなか難しいところもあります。たとえば預貯金について、「別居時残高-婚姻時残高」が婚姻後に形成された財産といえると思われる方がいるかもしれず、実際、弁護士でもそのように考えている方はそれなりにいるようです。もっとも、家庭裁判所の実務がそのように考えているわけではなく、たとえば定期預金のような日常的に入出金がそこまでない財産であればそのようにいえても、普通預金、それも日常的に頻繁に入出金されている口座であれば「婚姻時預貯金と別居時預貯金はすでに区別不可能なほどに混在してしまっているので別居時残高全額を共有財産と見るしかない。」というような判断がされるわけです。 この点について、とある裁判官の論文では、「夫婦の預貯金は全体として一つの家計を構成し、入出金を繰り返しながら変動していくのが通常であって、婚姻時の残高が、いわば夫婦共有財産の形成のための原資として費消されたと考えることができる。そうであるとすれば、この場合も、夫婦の一方の特有財産を原資の一部として取得・形成された財産(略)と同じく、原則として、基準時の残高全額を分与対象財産と評価した上で、婚姻時の残高については寄与度の問題として全体的な分与割合を認定する際に考慮すべきである。もっとも、婚姻期間が長くなれば現在の財産形成に対する婚姻時の預貯金残高の影響は小さくなるから、実質的婚姻期間が長期(例えば5年以上)にわたる場合には、分与割合に差をつける必要はないと思われる。」と指摘されています(山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」家庭裁判月報平成22年3月第662第3号)。そのため、筆者は、婚姻時残高を別居時残高から控除できるかという問題については、一応この「実質的婚姻期間が5年あるか」を念頭に検討しています。 「分与の割合」は、基本的に、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度により決まるという考え方が取られています。 夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。 こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したか判断するのは非常に難しい問題です。 そのため、実務上は、ほぼすべての事案で、共有財産形成への貢献度については5:5を当然の前提として進められます。稀にこの共有財産形成への貢献度を訂正するという事案もありますが、例えば、夫婦の片方の高収入がよほどの特殊な個人的技能によるものである場合(プロスポーツ選手や芸術家など)や、夫婦の一方が過度な浪費やギャンブルで夫婦共有財産を著しく毀損したことをいわゆるマイナスの貢献とみる場合であれば5:5の貢献度を訂正することもあり得るでしょう。後者のマイナスの貢献のパターンは実際には結構あり得るのではないかと思いますが、ただ当然のことながら、調停や裁判で浪費やギャンブルの証明をできるかというハードルはあり、これをクリアすることは容易ではありません。 相手の財産を把握しておかないと財産を隠されるリスクがあります。相手方が普段はあまり動かしていない口座も含めて銀行口座をもれなく把握しておくことや、株等の証券、保険なども財産性のあるものはきちんと把握しておく必要があります。別居後、こちらがきちんと情報を持っていない状況で、きちんと財産を漏れなく自ら開示してくる相手ばかりであれば楽なのですが、残念ながらそういう相手方ばかりではありません。 通帳についても、表紙の写真だけあればその口座の存在が分かるのでいいと思われるかもしれませんが、その引落しの履歴からは、保険料の支払(=保険契約の存在→積立性のある保険であれば当然財産になります。)、証券口座への資金の移管(=株や投資信託の存在が推認できます。)など重要な情報があることも多いです。表紙だけ写真で抑えて満足してはいけないのです。 給与明細から会社で掛けられている生命保険の存在が分かり、その生命保険に思いのほか高額の解約返戻金が出ることが判明したこともありますし、退職金の積立てがなされていることが判明することも多いです。 このような相手方財産の資料は、当然、別居してからは得られなくなるものではないので、同居中に時間をかけて収集しておく必要があります。同居中から弁護士にご相談いただければ、このような同居中の相手方財産収集に向けたアドバイスもさせていただきますので積極的にご相談ください。 財産分与請求は、離婚後2年以内であればできると期限が決まっているので、早めの請求を心がけましょう(なお、余談ですが、この財産分与の期限については法改正で若干延長するという動きがあるようです。)。 少なくとも現行法のもとでは、財産分与請求は離婚後2年以内にしておかなければいけないので、もし離婚から時間がたっている場合は早めに弁護士に依頼することをお勧めします。 協議で合意に至らなかった場合は、裁判所の手続きで決めてもらうことになります(もちろんこの事前の協議は、必ずしておかないといけないというものではありません。)。裁判所の手続きというものがどのようなものかは、離婚前か離婚後かで若干の違いはあります。離婚前なのであれば離婚自体と一緒に決める必要がありますので、離婚調停または離婚訴訟のなかで財産分与について決めていくことになりますし、離婚後であればすでに離婚の問題はないので、財産分与についてのみ調整してもらう財産分与調停という手続きをすることになります。 家庭裁判所で決めた、調停や審判などの取決めを守らない場合には、裁判所の手続きのなかで作成された調書という書類の効力をもとに強制執行することが可能になります。その中でも、給与差押えが一番効果的ですが、相手方が無職の場合や、個人事業の場合には、個別の財産を探し出して差押えをする必要があります。ここまでくると弁護士でないと対処が難しい場合も多いと思われますので、早めにご相談いただくのが良いと思います。ここで動き方を間違えると、相手方の財産隠しや強制執行逃れを誘発してしまうこともあります。 財産分与は、そもそもの夫婦双方が持っている財産の調査、その財産がどのように形成されたか、財産の評価はどうするか、分け方をどうするか、等様々な問題があります。財産分与について不安がある方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 「不動産の財産分与」について 財産分与のうち、不動産について、分与方法、ローン付き不動産の分与方法、税金などについて、ご説明いたします。 「財産分与」に関するQ&A よくあるご質問のうち、財産分与に関するご質問をまとめました。 解決事例財産分与(預貯金)が争点の事例 解決事例財産分与(保険)が争点の事例 解決事例財産分与(退職金)が争点の事例 解決事例財産分与(不動産)が争点の事例 解決事例財産分与(債務・借金)が争点の事例 解決事例財産分与(株式)が争点の事例 解決事例財産分与(その他)が争点の事例 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-zaisanfaq']
-

財産分与(不動産)
財産分与の対象には、預貯金だけでなく、不動産も含まれます。 まずは、不動産の時価を算定し、評価額を算出します。不動産会社に査定してもらったり、近隣で同じような物件の取引があれば、その価格を参考にしたりします。その他に、土地は路線価や公示価格を参考にしたり、不動産鑑定士に依頼したりする方法もあります。 不動産を分与する場合には、 売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける どちらかが所有し、分与の差額を現金で支払う 相手方名義の家に住み、賃借権を設定して家賃を払う 分与の割合に応じて共有する など、様々な方法があります。しかし、それぞれに良い点もあれば、悪い点もあります。 1.については、分け方が簡明であるというメリットがありますが、中古住宅であれば希望価格での売却が困難というデメリットがあります。 2.については、片方が従前の住まいと同じ場所に住むことができるというメリットがありますが、他方で差額の支払い能力がないと困難であるというデメリットがあります。 3・4については、支払い能力についてはあまり問題となりませんが、離婚後も相手との交渉を続けなければならないというデメリットがあります。 不動産を分与する場合には税金の問題もあるため(後述)、どういう分け方をするのかは慎重に選択すべきです。 ローンが残っている不動産の場合は、そうでないものと比べて財産分与が複雑になります。 まず、不動産の評価額ですが、不動産の時価から、残っているローンの額を引いた額とするのが一般的です。例えば、時価3000万円のマンションでローンが2000万円残っている場合には、3000万円-2000万円の1000円が分与の対象となります。 また、評価時期までに返済した元金充当分を分与の対象とする考え方もあります。例えば、時価3000万円のマンションで、離婚時までに返済したローンのうち元金充当額が2000万円であれば、この2000万円が分与の対象となります。 ローン付き不動産を分与する際には、不動産の名義、ローンの名義、ローンの残高、不動産の時価によっても違ってきますが、 所有権を取得した側がローンの返済をし、分与の差額があれば現金で支払う 売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける 所有権を取得しなかった側がローンの返済をする 等の形があります。 1.の場合、マンションの時価が3000万円でローンが1000万円残っているとすると、2000万円が分与の対象となります。分与の割合が2分の1ずつとすると、取得する側は、相手に現金などで1000万円を支払うことになります。取得する側がローンの名義人でなければ、名義の変更をしなければなりません。変更には債権者の承諾が必要であり、支払い能力がなければ承諾はされないでしょう。 2.の場合は、不動産の時価よりもローン残高が上回っている場合、売却しても債務がのこることになります。例えば、マンションの時価が1500万円で、ローン残高が2000万円であれば、売却後も500万円の債務が残ります、この債務について、分与の対象とすることもあります。 3.の場合は、例えば妻に不動産の名義を変更し、ローンの名義人である夫が離婚後養育費の代わりとしてローンを払い続けるという形も場合によっては考えられます。ただ、離婚後夫が任意にローンを支払うとも限りません。支払われなくなった場合、ローンの支払いの取り決めを公正証書でしてあれば強制執行の手段もありますが、夫に資力がなく、差し押さえる財産がなければ意味がありません。 また、妻がマンションのローンの連帯保証人になっている場合には、夫がローンを支払わない場合、妻にローンの支払い請求が一挙にされてしまいますので、そこには十分留意する必要があります。 お金を貸した側としては、担保として、連帯保証人をつけているわけですから、簡単に連帯保証契約を解除したり、他の親族に連帯保証人を変更したりすることは、弁護士を入れたとしても難しいところです。ですから、不動産の財産分与の際は、ローンについてしっかり把握し、その支払いについてどうするか、そこでの交渉であれば弁護士に依頼するメリットは十分あります。 不動産を分与する場合は、実際には売買していなくても、分与する側が資産を売却して得た代金を相手に支払ったものとみなされ、支払う側に譲渡所得税が課せられる場合があります。 居住用の不動産を分与する場合は、譲渡所得の特別控除(3000万円を限度とする・平成30年6月現在)が受けられます。さらに所有期間が10年を超える場合は軽減税率の適用が受けられます。ただし、この軽減税率は「親族以外の者への譲渡」に適用されるので、分与は離婚成立後に行うこととなります。 不動産を受け取る側には、「不動産取得税」と、不動産の名義変更の際に「登録免許税」が課せられます。また、不動産の所有者になると、毎年「固定資産税」が課せられます。 結婚20年以上の夫婦であれば、一方が自宅用の土地や建物や、土地・建物の取得金を贈与し、贈与された側が続けて住む場合は、2110万円(特別控除2000万円+通常の贈与税の控除額110万円)までは非課税です。 もっとも、不動産取得税・登録免許税はかかります。贈与した側にも税金は課せられません。この制度を使うか、財産分与をするか、比較考量して検討する必要があります。 不動産の財産分与については、評価から分け方まで様々な方法がありますので、争いの多い事案です。まずは一度、専門家にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 「財産分与」について 財産分与について、分与の対象となるもの、割合、気をつける点などについて、ご説明いたします。 「財産分与」に関するQ&A よくあるご質問のうち、財産分与に関するご質問をまとめました。 「財産分与(不動産)」が争点の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、財産分与(不動産)が争点であった事例をまとめました。 解決事例財産分与(預貯金)が争点の事例 解決事例財産分与(保険)が争点の事例 解決事例財産分与(退職金)が争点の事例 解決事例財産分与(不動産)が争点の事例 解決事例財産分与(債務・借金)が争点の事例 解決事例財産分与(株式)が争点の事例 解決事例財産分与(その他)が争点の事例 [myphp file='link-money']
-

婚姻費用
婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費などの生活費、子どもの教育費など、結婚生活を送るうえでかかる費用のことをいいます。 概念的には、同居、別居に関わらず、夫婦間で受け渡される生活費は婚姻費用であり、別居後に請求する生活費だけが婚姻費用になるわけではないのですが、同居中は各家庭のルールにより生活費分担がされていることが多いので、ある程度定型的なルールに従って算定される婚姻費用が問題になるのは主に別居後のことになります。 民法には、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する義務がある旨を定めています。妻が専業主婦で収入が少ない場合や、パート勤務などで夫より収入の少ない場合は、夫は生活費を渡す義務があります。なお、勘違いしないでいただきたいですが、婚姻費用は、必ずしも夫から妻に支払う必要がある金銭というわけではなく、男女問わないものです。しかし、やはり現実には、妻のほうの収入が低いケース、あるいは別居後は妻が子どもと監護するケースが多いので、妻から夫へ婚姻費用請求するケースが多いというだけです。 本記事では、単に婚姻費用の請求権者を「妻」と記載しますが、状況によっては夫から妻に請求できることもあることはご認識のうえ読んでください。 さて話を戻しますが、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚成立までは法律上は婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。 ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければならないわけです。 例外的な事情として、婚姻関係の破綻に主たる責任がある配偶者(これを「有責配偶者」ということがあります。例えば、不貞をして別居の原因を作った配偶者などです。)からの婚姻費用請求は、一部制限されることがあります。妻が不貞して家に出て行ったのに婚姻費用請求されては、不貞をされた夫としてはたまったものではありませんし、そのような場合に裁判所が婚姻費用請求を制限するというのは、一般的な感覚からしても正しいと感じられますね。ここで「一部」制限されると留保を付けたのは、婚姻費用は、いわば『子どもの養育費に「婚姻費用を請求する配偶者自身」の生活費を合算した額』であり、有責配偶者からの婚姻費用請求で制限されるのは、後者の「婚姻費用を請求する配偶者自身」の生活費部分だけで、子どもの養育費部分は制限されないからです。妻が不貞して子どもを連れて出て行ったからと言って、子どもにそのしわ寄せが来るのは避けるべきとの考えです。これも一般的な感覚から言っても正しいのではないかと思います。 婚姻費用の金額や支払方法に特に決まりはありませんが、ご想像に難くないとおり、別居、離婚協議、離婚調停など揉めに揉めている夫婦間で、夫婦の話合いで生活費を支払えと妻が請求して夫が素直に支払うケースは多くはありません。そのため、揉めた場合には弁護士ないし裁判所の出番となるわけですが、弁護士や裁判所が婚姻費用について定めるときに夫婦独自のルールや慣習を元にしていては処理に統一性を欠くので、弁護士や裁判所は、通常は裁判所が公開している婚姻費用算定表を用います。これはネット検索していただければこれはすぐ出てくると思います。一つ注意点として、この算定表は数年前に改定されているので、うっかり古い算定表を参照したりしないよう注意しなければなりません(うっかり古いものを使うと婚姻費用が低めにはじき出されます)。 ただこの算定表は、簡易に婚姻費用をはじき出すツールではありますが万能ではないことに注意すべきです。そもそも相手方の収入が分からなかったり、自営業で額面収入を操作されているとこの算定表を使えなかったり不相当な金額しか出てきません。 また、どちらかに前配偶者との子ども(いまの配偶者との養子縁組などはないことを前提とします。)などがいるなど、イレギュラーな事案では、この算定表を使えません。そのような場合は、この算定表の背後にある考え方に従い個別に計算をしていくしかありません。 算定表は、元をただすと「司法研究報告書第70輯第2号『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』」という論文に端を発するのですが、この論文に示された考え方であったり、これまで実務で集積されてきた裁判例をもとにして計算をしていくことになります。そこまでいくともはや弁護士でなければ対応が難しい場合もあるでしょうから、家事事件の取扱い経験が多い弁護士へのご相談をお勧めします。 婚姻費用の支払義務や金額について、相手が話合いに応じない場合や、話し合っても合意に至らない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担」を求める調停(婚姻費用分担調停)を申し立てます。 家庭裁判所の調停では、夫婦の資産や収入、支出などについて双方から話を聞いたり、解決案を提示したりしながら話合いを進めます。 婚姻費用の始期(要するにどの月から支払義務が生じるか)については諸説あるのですが、実務上多く取られているのは、請求時(明確に婚姻費用請求をした日が属する月)あるいは婚姻費用分担調停の申立てをした月(もう少し正確に言うと家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申立書が受け付けられた月)となります。そのため、別居してからいつまでも婚姻費用請求をせず、調停申立てもしないと、毎月の権利が消滅すると言うことになるので、別居したらできるだけ早く申し立てをしたほうがよいでしょう。例を挙げると、1月31日に別居して2月1日に婚姻費用分担調停の申立てをすると支払ってもらえる婚姻費用は2月分からになりますが、これをもう少し頑張っていただき、1月31日の家庭裁判所が動いている時間帯までに婚姻費用分担調停の申立書を提出してその日中に受付の処理をしてもらえば、1月分から婚姻費用が取れる可能性が高いので、「ひと月分も漏らさず婚姻費用を取りたい!」という方はそこまで考えて動きましょう。 妻が専業主婦などで、実家にも頼れず、子も小さい場合、すぐに婚姻費用の支払いがなければ大変です。 裁判所の調停・審判には時間がかかるので、上記のような場合には、調停・審判の申立てとともに「審判前の保全処分」の申立てをします。裁判所の判断で、「毎月~万円支払え」という仮の婚姻費用の支払が命じられます。そして、その後調停・審判をじっくりすることにより出た結論が保全処分による仮の婚姻費用額とずれる場合には、事後的に清算をすることになるのです。 婚姻費用に関してこの「審判前の保全処分」をするケースは多くはありません。しかし、別居後にすぐ婚姻費用分担調停をしても、相手方が粘ってくると調停ないし審判での結論が出るまで半年以上の期間が経過してしまうことはかなりあります(なおその間の婚姻費用は未払分として一括の支払命令が出ます。)。そのため、そのような場合、別居するほうの選択肢としては、調停ないし審判で決まるまでは自分の収入だけで生活を回す、あるいは誰かの援助を得る、ということのほかに、「審判前の保全処分」で仮払いを受けつつ別居先での生活を落ち着かせる、ということも考えるべきです。頼れる実家もなく別居後の生活の目途が立たないからといって別居を諦めるべきではないのです。 ただ、単に婚姻費用分担調停をするくらいであれば弁護士を立てずに手続を取る方も多いでしょうが、この「審判前の保全処分」までするとなるとかなり難易度が上がるので、弁護士へのご相談はしたほうがよいでしょう。 弁護士からの手紙によってすぐに支払いをしてくるケースも少なくありません。また、交渉では、弁護士が間に入りますので、相手と直接やりとりするストレスから軽減されます。 調停等も、弁護士が同行します。弁護士を頼むメリットはたくさんあるので、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 「婚姻費用」が争点の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、婚姻費用が争点であった事例をまとめました。 [myphp file='link-money']
-

年金分割
熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。 たとえば、夫がサラリーマンで妻がずっと専業主婦だった場合、老後の年金は夫と妻それぞれの名義の国民年金(老齢基礎年金)と、夫名義の厚生年金(老齢厚生年金)を受け取ることになっています。離婚すると、妻が老後にもらえる年金は国民年金だけになり(独身中に厚生年金に加入していた場合は、その分の厚生年金を受け取ることができます)、夫と妻の受け取る金額には大きな差が出てしまいます。 しかし、夫が外で精一杯働けるのは妻のサポートがあってこそです。また、家事や育児に追われて男性並に働きたくても働けないという女性もいらっしゃいます。 家事労働は、そのままでは年金に反映されないため、「結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう」という制度が「年金分割」です。 年金分割制度には、「合意分割」と、「3号分割」の二つがあります。 離婚をしたときの年金分割制度は厚生年金や共済年金を対象にした制度です。夫婦ともに国民年金のみに加入している場合には対象になりません。この分割制度には、「合意分割制度」と、「3号分割制度」の2種類があります。 また、年金分割は厚生年金や共済年金の標準報酬部分に限られ、基礎年金部分や厚生年金基金のような上乗せ部分は対象になりません。いずれも、請求は離婚後2年を過ぎるとできなくなります。 参考資料 1階部分 (老齢)基礎年金 受け取る金額は年金の種類にかかわらず、一定額となる 国民年金で受け取れるのはこの部分のみ 2階部分 報酬比例部分 年金保険料が給与額をもとに決まるため、給与が高いほど保険料が高く、年金額も高くなる これを受け取れるのは、厚生年金や共済年金の加入者のみ 3階部分 企業年金 (厚生年金の場合) 職域相当部分 (共済年金の場合) 会社ごとにある上増し年金。 同じ金額の年金を受け取れる確定給付年金と、同じ金額の保険料を払うが、受け取れる年金額は年金の運用実績により左右される確定拠出年金がある これを受け取れるのは、厚生年金や共済年金の加入者のみ 第1~3号被保険者 第1号被保険者:日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方) 第2号被保険者: 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方(ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます) 第3号被保険者:第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方 ※ 第3号被保険者は、自身は年金保険料を支払うことなく、1階部分の老齢基礎年金を受け取れます。 当事者間で年金分割の割合を決めるのが、「合意分割」です。 合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が、結婚していた期間に応じて、その期間の厚生年金・共済年金の標準報酬を最大2分の1まで分割できる制度です。分割の割合は夫婦の話し合いで決め、決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めます。 割合についての合意ができたら年金事務所に年金分割の請求をする必要があります。 分割の話し合いをするにあたっては、分割の対象になる婚姻期間や厚生年金の標準報酬額について正確に知る必要があります。そのための情報は、日本年金機構が「年金分割のための情報通知書」を提供することになっています。情報の請求は当事者が一緒に、または一方からすることができます。 請求により2分割されるのが「3号分割」です。 3号分割は、専業主婦の方が対象です。平成20年4月から離婚するまでの間、第3号被保険者であった期間の夫の厚生年金の標準報酬額の2分の1を、話し合いや調停などによらずに受け取ることができます。 たとえば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の夫婦が平成30年5月に離婚した場合、平成20年からの10年間分に相当する厚生年金の標準報酬額の半分が妻名義になります。それ以外(平成20年3月以前や妻が厚生年金に加入していた期間など)の夫名義の厚生年金や、共働きの場合の分割については、合意分割の制度に従って決めます。 なお、3号分割は、離婚をすると自動的に年金が分割されるわけではないため、離婚後、第3号被保険者であった本人が年金事務所に分割の請求をする必要があります。 婚姻中に相手方が厚生・共済年金に加入しており、その扶養に入っていた場合には、離婚後に当然に相手方名義の厚生・共済年金を受け取ることはできません。また、老後に受け取れるのは国民年金のみ、又は自身で厚生・共済年金に加入したとしても加入期間が短く年金も低額であることも想定され、老後の生活費が不足するおそれもあります。そのため、年金分割をしない場合には、将来受け取れる年金の受給額が減少することになり、老後の生活費が不足するということにもなりかねません。このようなデメリットの大きさや老後の金銭的な不安は精神的な負荷等を考慮すれば、老後の生活を少しでも安心して過ごせるよう年金分割を行っておくことは必須といえます。 なお、次に記載してあるとおり、年金分割も請求できる期間に制限がありますので注意が必要です。 年金分割の請求は離婚が成立した後でも行うことができます。しかし、年金分割請求ができる期間にも制限があることに注意が必要です。この期間制限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年です。ただし、例外として、離婚してから2年を経過するまでに審判又は調停を申し立て、審判が確定又は調停が成立した場合には、その確定又は成立日の翌日から6ヶ月経過するまで年金分割請求を行うことができます。 以上のとおり、年金分割が請求できる期間は原則として離婚が成立した日の翌日から2年です。期間制限に例外があるとしても、この例外の適用を受けるためには調停又は審判の申立てが必要であるため、その準備期間も考慮しなければなりません。その他必要書類の取得などに必要な期間もあります。そのため、2年という期間があるとしても、年金分割に向けた行動を早期に取る必要があります。もっとも、年金分割は老後の生活に直接影響する制度ですが誰かがその存在を当然に知らせてくるものではありません。そのため、できる限り、離婚を検討する際に弁護士に相談し、離婚時に請求すべきものを把握しておくことも重要といえます。 年金分割は、熟年離婚に際して必ず決定しておいたほうが良い事項です。3号分割であれば、相手方の合意なくしてできますので、ご依頼となった際は、その手続きのお手伝いをさせていただきます。また、交渉によって企業年金部分の分割も請求していくことで、さらに多くの年金を受給できる可能性がございます。 熟年離婚する際には、年金分割が大きな関心ごとになるかと思います。手続きも煩雑になりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 「熟年離婚」のご相談 熟年離婚で気をつけるべき3つのことについて、弁護士が解説いたします。 「年金分割」が争点の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、年金分割が争点であった事例をまとめました。 [myphp file='link-money']
-

退職金
離婚時に、すでに支払われている退職金は、婚姻期間に対応する部分については、財産分与の対象となります。配偶者の寄与は、同居期間に按分した額を対象額として、原則2分の1の寄与が認められることが多いです。 また、近い将来支払われることがすでに確定している退職金は、財産分与の対象となりえます。 「なりえます」と述べたのは、将来の退職金は、事故、病気、懲戒解雇、勤務先の倒産、経営不振による減額など不確定要素があり、その受給が確実でないからです。 しかし、退職金は賃金の後払い的性格があること、勤労世帯にとっては年金と同様、老後の生活保障として重要であることなどから、その支給を受ける蓋然性が高い場合には、財産分与の対象とされています。 問題となるのは、何年先の退職であり、どういった勤務先であれば支給の蓋然性が高いと認められうるのか、蓋然性の低い場合にも何らかの事情として考慮するのか、清算対象とする場合の具体的な計算方法、支払い時期等ですが、これは事案ごとに裁判所の判断にゆだねられており、基準は明確ではありません。 しかし、退職まであと数年で、公務員等の退職金を受け取ることのできる可能性が高い業種であれば、将来の退職金が財産分与の対象となる可能性は高いでしょう。 配偶者が退職していない場合の退職金の財産分与の金額について、最近の公表例は少ないですが、実務では、別居時に退職したと仮定した場合の退職金額を、配偶者との同居期間に按分した額に修正し、それを折半するものが多いように思われます。 実際には、一括払いが多いように思われます。しかし、将来支払われる退職金については、退職金を支給された時点で支払え、と判断した裁判例もあります。 将来支払われる退職金については、もちろん配偶者の手元にないわけですから、事実上一括払いが無理である場合も十分あり得ます。そういった場合には、退職金については支給された時点で支払うとの文言を公正証書に残し、退職金が支給された時点で請求すること、任意に支払われない場合には強制執行をかけること等を検討するほうが良い可能性もあります。 どちらにしろ、退職金は一般的に夫婦の共有財産の中でも大きな割合を占めます。その点についてしっかりと決めておくことで、離婚後の生活をスムーズに送ることができます。 退職金の財産分与についてご不安な場合は、弁護士にご相談することをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 「熟年離婚」のご相談 熟年離婚で気をつけるべき3つのことについて、弁護士が解説いたします。 「財産分与(退職金)」が争点の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、財産分与(退職金)が争点であった事例をまとめました。 [myphp file='link-money']
お子様がいる方
-

親権を決める際にやりがちな禁止行動
親権を決める際にやりがちな禁止行動 違法な連れ去り行為、面会交流の禁止など 裁判所が親権を決定する際の判断基準 よくあるご質問のうち、財産分与に関するご質問をまとめました。 親権について お子様について決めておかなくてはならないことなど 現状尊重の基準(継続性の原則)が優先されるのであれば、先に子供を連れ去り、監護養育の実態を作ってしまえば良いのではないかと考えがちです。 しかし、同意を得ないままでの連れ去りは違法な連れ去りと評価されかねず、子供の引渡し請求等の法的手続を別途取られかねません。特に、過去に監護をそれほど担っていなかった方による連れ去りは違法と評価されがちであり、お子様の環境が短期間で何度も変わりかねません。 したがって、違法な連れ去り行為はお勧めできません。 裁判所は、必ずしもフレンドリーペアレントルールを重視しているわけではありませんが、合理的な理由が一切無い中で面会交流を一方的に禁止することはお勧めできません。通常、お子様にとっては両親双方がそれぞれ大切であり、親の事情のみで親子の絆を断ち切ってしまうのは、その後のお子様の成長にとっても好ましくないからです。 親権の判断基準の一つとして、「子の意思の尊重の基準」というものが存在することもあり、親権取得を希望する親はとかく相手側の悪い部分を吹き込みがちです。もっとも、このような行為はお子様を双方の両親の間に立たせることになり、お子様の精神面にとって極めて重い負担を与えかねません。 あまりに悪質な場合は、親権者として不適切という烙印すら押されかねませんので気を付けましょう。 [myphp file='link-child']
-

裁判所が親権を決定する際の判断基準
親権を決める際にやりがちな禁止行動 違法な連れ去り行為、面会交流の禁止など 裁判所が親権を決定する際の判断基準 よくあるご質問のうち、財産分与に関するご質問をまとめました。 親権について お子様について決めておかなくてはならないことなど 法律上、親権者指定の具体的な基準は定められていません。 一般的には、父母の双方の事情(監護に関する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性など)や、子の側の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性、子自身の意向など)などを比較考量しながら決定されるべきものとされています(松原正明「家裁における子の親権者・監護権者を定める基準」『夫婦・親子215題』判例タイムズ747号305頁)。 他方で、不貞行為や暴力行為などの離婚原因の基礎となった事情は、当然に親権を決定する際の判断基準となるものではありません(もちろん、不貞行為に及んだ結果、子供の福祉に悪影響を及ぼすようなことがあれば間接的に親権の判断に影響を与える可能性は十分にあります。)。 その上で、裁判所で親権を決定するにあたっては、以下の代表的な考慮事情が主な判断要素となることが多いです。 従前、主に監護を担ってきた者が引続き監護を担うべきという考え方です。 他の考慮事情と比べても圧倒的に重視される傾向があり、特段の事情が無い場合、多くのケースで現状尊重の基準(継続性の原則)をベースに親権の判断がなされがちといっても過言ではありません。 父親側のご相談者の方から「親権はどうせ母親が有利なんでしょ?」という嘆きともとれるご相談を頻繁にいただきます。 もっとも、母親優先の基準は必ずしもお子様の年齢にかかわらず常に優先されるものではなく、授乳が必要な場合等、生理学上どうしてもお子様にとって父親よりも母親が重要となる乳幼児期に限られます(この点は色々な考え方が少なくとも筆者はそのように考えています。)。 「親権はどうせ母親が有利」という結果は、生理学上の母親か父親かという違いによるものというよりも、むしろ日本の多くのご家族が、いまだに父親が主に就労により生活費を得て、母親が主にお子様の監護を担ってきたという社会的役割によるところが多分にあり、「母親優先の基準」というよりも「現状尊重の基準(継続性の原則)」によって結果的に母親が親権を取得することが多いということだと考えられます。 したがって、仮に母親が父親と同様、あるいはそれ以上に就労に従事し、父親が主にお子様の監護を担ってきたようなケースでは、お子様が乳幼児期でない限りは当然に母親が優先されるわけではありません。 どちらが親権者になるかはお子様にとっても極めて重要な事項の為、お子様の意思は当然重視されるべきものです。もっとも、お子様の年齢によってはそもそも意思表示ができない、あるいは十分な判断能力を有していない等の理由にとって、必ずしもお子様の意思を重視すべきではありません。 この点、お子様が15歳以上である場合は、裁判所でお子様の陳述が聴取されることが法律上必要となっています。またお子様が概ね10歳前後程度に達している場合も、何らかの形でお子様の意見が聴取されることが殆どです。 ただし、お子様は監護の状況や見通し等によって、本心とは異なる意見を述べられることも少なくありません。お母さんの機嫌が悪くなるので、本当はお父さんに会いたいけどあえて会いたくないと話すお子様もいらっしゃいます。 裁判所もそのような事情は十分に熟知している為、お子様の意思は可能な限り聴取するものの、他の事情を総合して親権者を判断するのであり、お子様の意思のみをもって親権者を指定することは殆どありません。 一切親権が取れないという状況を回避する為、夫婦間で兄弟姉妹を分離して親権を取得しないかという提案がなされることがあります。もちろん、協議段階であれば夫婦間のみで親権を決めてしまうこともできますが、裁判所は基本的に兄弟姉妹を分離すべきではないと考えています。 裁判所では、比較的重視される基準です。 Q1 相手と比べて収入が低く生活が安定していないが親権を取れないのか。 A1 経済的事情は親権の一つの判断要素となります。もっとも、通常は、養育費という形で夫婦の収入差は一定程度是正されますので、余程極端な状況でなければ収入が低いことのみを理由に親権が取れないということはありません。 そもそも、幼いお子様の親権を取得し、監護・養育を一人で担うとなれば従前通りにフルタイムで働くことは容易ではありません。実際、多くのケースで専業主婦の方、あるいはパートタイムの方がお子様の親権を取得されています。 Q2 相手の不貞行為によって離婚せざるを得なくなったのに親権までも取られてしまうのか。 A2 残念ながら不貞行為自体は直接的に親権の判断基準となるものではありません。他方で、不貞行為に及んだ結果、子供の福祉に悪影響を及ぼすようなことがあれば間接的に親権の判断に影響を与える可能性は十分にあります。 Q3 面会交流の実施の有無は親権の判断基準になるのでしょうか。 A3 面会交流の実施の有無も一定程度親権の判断基準になり得ます。一般的にフレンドリーペアレントルールと言われ、面会交流に協力的な親権者を面会交流に非協力的と比べて親権者に指定すべきという考え方が存在します。 もっとも、一切面会をさせないといった極端な事例であればさておき、一般的な範囲で面会交流を認めていれば、必ずしも相手がより自由な面会交流を認めていたとしても当然に親権をできなくなるというわけではありません。 なお、近年ではフレンドリーペアレントルールを重視した平成28年3月29日千葉家庭裁判所松戸支部判決(第1審)を退けた平成29年1月26日東京高裁判決(第2審)に対する父親側の上告を棄却した平成29年7月12日最高裁第二小法廷決定が非常に有名です。 [myphp file='link-child']
-

親権
親権を決める際にやりがちな禁止行動 違法な連れ去り行為、面会交流の禁止など 裁判所が親権を決定する際の判断基準 よくあるご質問のうち、財産分与に関するご質問をまとめました。 親権について お子様について決めておかなくてはならないことなど 離婚の際、未成年のお子様がいる場合には、お子様について決めておかなくてはならないことがあります。 離婚前に決めておく必要があるのは、主に 父母のどちらが親権者となるのか お子様を引き取らない側が負担する養育費の支払い額と支払方法 離婚後のお子様の戸籍と名乗る姓 引き取らない側の親とお子様との面会をどのように行うか 以上の4点です。 ここでは、1.について解説いたします。 親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の二つがあります。「身上監護権」とは、お子様の衣食住の世話をし、教育やしつけをする権利と義務のことです。「財産管理権」とは、その名の通り、財産を管理する能力のない未成年に代わって法的に管理し、契約などの代理人になる権利と義務のことです。 通常は、お子様を引き取った親が親権者となり、日常的な世話、教育をすることが多いため、親権と監護権が同一人に帰属します。 もっとも、親権の取り合いで争いになった場合に、まれなケースですが、親権から身上監護権のお子様の世話や教育の部分の権利と義務を分けて、親権者と監護権者に分けることで解決をはかることもあります。つまり、親権者ではない親がお子様を引き取り、監護権者としてお子様の日常的な世話や教育、しつけを行うことになります。 親権者 →財産管理権の部分の権利と義務を負う 監護権者→身上監護権の部分の権利と義務を負う お子様が複数いる場合には、それぞれの親権者を決めなければなりません。お子様への精神的な影響を考えると、原則として兄弟姉妹は同一の親権者であることが望ましいとされていますが、お子様の年齢や親の資力等の様々な事情によって、親権者が父母別々になることもあります。 離婚届には、未成年のお子様の親権者を記入する欄があります。協議離婚の場合は、親権者が決まっていないと離婚届けが受理されず、離婚はできません。 親権の取り合いになり、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。離婚調停とともに、親権者の指定を申し立てることもできますし、親権だけの調停を求めることもできます。調停もあくまで話し合いの場なので、調停で決まらない場合には、最終的に裁判で決着をつけることとなります。裁判離婚では、家庭裁判所が離婚を認めるときに親権も指定します。 ※クリックで大きい画像が開きます 家庭裁判所が親権を決めるときには、特別な事情がない限り、乳幼児であれば母親が優先されています。これは「母性優先の原則」と呼ばれています。乳幼児にはどうしても授乳が必要であるため、母親と子が共にいるほうが、お子様のためになるからです。 また、お子様の現在の生活環境を維持するため、育児の放棄などの問題がない限り、実際に子を監護養育している親を優先します。これは、「継続性の原則」と呼ばれています。子がこれまで育ってきた環境を変えないことが、子のためになるからです。 したがって、離婚に先駆けて別居する際は、親権を取得したい場合には、お子様を連れて出た方がよいでしょう。 お子様が二人以上いる場合には、基本的には兄弟姉妹は同一の親権者が指定されることとなります。これまで一緒に育ってきた兄弟姉妹が離れ離れになってしまうことは、お子様にとって多大なストレスになるからです。 親権者となる親が心身ともに健康であること、お子様に接する時間が多いことも判断材料の一つです。 子が満15歳以上であれば、裁判所は子の意見を聞かなければならないことになっています。満15歳未満であっても、お子様の発達状況によってはお子様の意思が考慮されます。 妊娠中に離婚した場合は、母親が親権者になります。ただし、出産後に話し合いによって、親権者を父親に変更することもできます。 離婚後の親権者の変更は父母の話し合いだけではできません。親権者の変更を求めるときは、家庭裁判所に親権者変更の調停または審判の申し立てをしなければなりません。申し立てはお子様の父母に限らず、おじ・おばなど親族でも可能ですが、子自身からはできません。 親権者の変更が認められるのは、親権者が病気になりお子様の世話ができなくなった場合や、お子様を虐待する、お子様の養育環境が著しく変化した、など、親権者の変更がお子様にとって必要とされる理由のあるときのみです。 家庭裁判所の調査官は事実の調査を行い、親権者の変更がお子様の福祉と利益のために必要かどうかを判断します。お子様が満15歳以上の場合はお子様の意見を聞き、その意見を尊重します。親権者変更が確定したら、確定した日から10日以内に市区町村役所の戸籍係に親権者変更を届け出ます。 なお、親権者と監護権者を別々に決めていた場合で監護権者を変更したいというときには、当事者の話し合いだけで決めることができます。 親権について当事者間で全面的に争いがある場合、なかなか当事者間で協議が進むことはありません。金銭や物のように分割することができないのはもちろんですが、それ以上にそれぞれのお子様に対する様々な想いがある為、協議段階で譲り合って解決という結論になりにくい為です。 その為、親権について全面的に争いがある場合、どうしても調停や訴訟といった手続に移行しがちになります。 当事者間の協議と異なり、調停・訴訟手続は家庭裁判所を利用した手続です。調停手続自体はあくまで家庭裁判所で実施するお話合いの手続ではありますが、大きな特色として、親権が争点になっている際は、いわゆる家庭裁判所の調査官が、公平な第三者としてお子様の監護状況や意向調査を実施し、親権者の適正について報告書を作成される点にあります。もちろん、調停段階ではあくまで参考意見にとどまり、裁判官等が強制的に親権者を指定するわけではありませんが、仮に調停が不成立となり、訴訟を申立てた際も親権を決定するにあたっての重要な資料となります。 その為、調停段階から、いかに家庭裁判所の調査報告書にどのような記載がなされるのかを意識した上で対応する必要があります。 どの範囲において調査を行うかは個別具体的な事情によって様々です。ただ、一般的な調査対象や手順としては以下の流れになることが多いです。 ⑴ 事前に「子の監護に関する陳述書」を作成 現監護者は、現在のお子様の監護状況を中心に、非監護者は今後親権者となった場合にどのように監護していくかを中心にお子様の監護状況について書面で説明をしていくことになります。現在のご収入や就業先、お子様の監護を補助して下さる監護補助者の有無や健康状態、自宅の間取り等、お子様の監護状況について可能な限り詳細を記していくこととなります。 子の監護に関する陳述書に記載した内容が当然に事実として調査官や裁判所に認めていただけるわけではありませんが、各種調査の際に参考にされるものとなる為、調査委に際して着目していただきたいポイントについては特にこの段階で強調しておく必要があります。 したがって、子の監護に関する陳述書を作成するにあたっては、親権がどのように判断されるかについて詳しい弁護士に確認していただくことをお勧めいたします。 ⑵ 当事者がそれぞれ別に家庭裁判所に呼ばれ、調査官よりヒアリングを受ける。 子の監護に関する陳述書の記載を元に、実際に調査官がお父様又はお母様と直接お会いし、双方のご意見を伺います。 あくまで、双方の言い分を確認し、整理することが前提となっている為、陳述書同様、このヒアリングの際に話した内容が当然に事実として調査官や裁判所に認めていただけるわけではありません。その為、相手の主張されている言い分について一喜一憂される必要はありませんが、他方で、この段階でお伝えされるべき事項をお伝えしないままだと、親権を判断するにあたって重要な事情が調査官や裁判所に伝わらない場合もあります。 多くの方は、そもそも裁判所という場所に行くこと自体もなかなかありません。また、調停委員とは、調査官とはどのような方々なのか、裁判官とは何が違うのかもあまりよく分からないという方々が殆どなのではないでしょうか。そのような中で、きちんと調査官に対して伝えるべき事情を伝えるということは決して簡単なことではありません。 弁護士に依頼されている場合、弁護士がこのような調査官調査に同席し、随時サポーえいただく必要はありますが、「見落としている部分がないか」等も含めて弁護士がお手伝いさせていただくことがより盤石の体制を整えることができます。 ⑶ 現監護者の自宅訪問調査 以上の経緯を踏まえ、実際に調査官が現監護者のご自宅に伺って監護状況を確認する場合がございます。ご自宅の間取りや衛生状況がお子様を監護するに際して適切な状況なのか、現監護者を親権者として指定して良い程度にお子様との関係が円満に築かれているのか等が調査官の目で実際に確認されることとなります。 ⑷ 幼稚園、保育園、学校等の関係者調査 お子様のご年齢や状況によっては、別途お子様が通われている幼稚園、保育園、学校等の教育施設でも調査が実施される場合があります。担任の先生等、監護者とは別の視点でお子様を日々見られている方の意見等が参考になる場合も多いからです。 ⑸ 調査報告書の作成 以上の調査を踏まえ、調査報告書が作成されます。概ね調査命令が出されてから2か月前後で報告書が作成される傾向にあります。調査報告書の記載内容は様々ですが、親権者が争点の場合、最終的に当事者のいずれが親権者として適切かと明記されることになります。訴訟段階においては、家庭裁判所の裁判官が実際にはお子様に直接お会いしたり家庭訪問をしたりするわけではない為、親権を判断するにあたってはこの調査報告書の結果が非常に重視される傾向にあります。 もっとも、調査報告書の結果自体が万全なわけではありません。調査段階では明らかでなかった事情や見過ごされている事情がある場合もあります。そのような場合に、きちんとそのような事情にスポットライトを当て、法的な主張立証を尽くすことで調査報告書の記載とは異なる結論となる場合も決してないわけではありません。 したがって、調査報告書の結果がどのような内容であっても、決して油断せず、また諦めずに対応していくことが重要です。 親権を争う前段階として、いわゆる監護権が争点となるケースが頻繁しております。昨今、子の連れ去り問題がフォーカスされがちで、その是非については本稿では触れませんが、実際に子の連れ去りに伴って子の引渡し請求、監護者指定という手続を申し立てる場合、あるいは申し立てられる場合が少なくありません。 一概には言えませんが、多くのケースではお子様の監護状況を極力何度も変更しない方が良いだろうという考えが働きがちなため、お子様が連れ去られてから時間が経過し、監護実績が積み重ねられてしまうと、仮にその段階で子の引渡し請求をしたとしても引渡しが認められる可能性が少なくなりかねません。その為、お子様が連れ去れた場合は、速やかに子の引渡し請求及び監護者指定の手続を行う必要があります。 また、その際はいわゆる「本案」手続のみならず、より早く期日を行う「保全」手続も同時に申し立てることをお勧めいたします。「本案」手続の場合、最短でも初回期日が1か月以上先になることが多いですが、「保全」手続の場合、早ければ1週間後に最初の審尋期日が設けられる場合もある為です。もちろん、「保全」手続が認められる為にはお子様を直ちに引き渡すべき緊急の必要性が存在することが要件となり、容易ではありませんが、少なくとも手続が早期に開始され、面会交流の実施も含めてお子様との接点をできるだけ早くに回復するという意味で非常に重要です。 このように子の連れ去りに伴うお子様の監護権が問題となるケースでは、子の引渡し請求、監護者指定の手続、保全手続等の知識・経験が不可欠です。 親権、監護権の問題は、調査官調査にどのように適切に対応していくのかが非常に大切です。また、子の連れ去り事例はいかに迅速に各種手続を進めていけるかが結論を大きく左右しかねません。大切なお子様の親権・監護権について全面的に争われている場面においては、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めいたします。 親権は、取れるか取れないか、いわば100か0かの争いなので、夫婦双方が譲り合わない場合が非常に多いです。弁護士に相談することによって、親権をとるための戦略や、そもそも親権をとらない代わりに面会交流を増やす交渉をしたほうが得策であるのではないか等、あなたとあなたのお子様にとって一番よい方法を一緒に考えていくことができます。 親権争いは、離婚するうえでご本人にとって最も精神的負担が多いことの一つです。また、夫婦双方が感情的になってしまい、まとまるものまとまらない、ということも多々あります。弁護士が間に入ることによって、冷静な話し合いができ、ご自身の負担も減らすことができます。親権争いでお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 「親権」に関するQ&A よくあるご質問のうち、親権に関するご質問をまとめました。 「親権」が争点の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、親権が争点であった事例をまとめました。 子どもの連れ去り緊急相談室 配偶者やその家族に子どもを連れ去られてしまった場合、早急な対応が重要です。なるべく早い段階で、当事務所にご相談ください。 [myphp file='link-child']
-

面会交流
離婚の際、未成年のお子様がいる場合には、お子様について決めておかなくてはならないことがあります。 離婚前に決めておく必要があるのは、主に 父母のどちらが親権者となるのか お子様を引き取らない側が負担する養育費の支払い額と支払方法 離婚後のお子様の戸籍と名乗る姓 引き取らない側の親とお子様との面会をどのように行うか 以上の4点です。 今回は4.について解説します。 お子様と離れて暮らす親には、離婚後、お子様と会ったり、連絡を取ったりする権利があります。これが、面会交流権です。面会交流については、民法766条に定めがあります。 面会交流について定めることなく離婚をすることは可能ですが、離婚前に決めておくことをお勧めします。離婚が成立した後では、自己に有利な面会交流を行うための交渉材料が少なくなってしまいますし、離婚に関することは一度に決めておいたほうが、後の紛争を防止することにもなるからです。 面会交流については、例えば以下のような事項について取り決めておくことが考えられます。 ・面会の頻度(1ヶ月に何回会うのか等) ・面会の時間(何時間会うのか等) ・面会の場所 ・連絡方法 ・宿泊の有無 ・お子様の受け渡し方法 ・学校行事・特別な日の面会交流 ・長期休暇の場合 ・間接的な交流の方法 ・小遣いやプレゼントの可否 以上のような事項を話し合いにより取り決めておき、話し合いがまとまった場合にはそれを書面化しておくことも重要です。口頭での合意では、時間の経過ととも合意内容が不明確となったり、相手方がのちに同意はしていないなど話をしてくるリスクもあります。なお、後述のとおり、どこまで具体的に合意書に記載するかはよく検討する必要があります。 面会交流の回数や方法については、もちろん、当事者間で合意が取れ、実施が可能であればその内容とすることになります。もっとも、面会交流の回数や頻度については月1回程度が目安と考えられます。 また、方法についても、単に面会するだけの場合もあれば、旅行に行く、学校行事に参加をするといった様々なものが考えられます。そのほか、間接的に接触する方法として電話、手紙、メール又はテレビ電話といったものも考えられます。そのため、合意書に全てを網羅する形で柔軟に面会交流をするために、「子の福祉を考慮し、当事者間で事前に協議して定める」と合意をしておいて、合意書の条項を抽象的なものにすることも一般的です。もちろん、事前の協議が難しいことも想定され、仮に調停で合意をする場合で面会交流に関する強制執行を想定されるような事案の場合には、「面会交流の場所は、申立人の住所地とする。」と明確に場所を定めることもあります。 仮に、当事者間の合意ができず、調停もまとまらない場合には、裁判所が子の福祉に適うようこの年齢、性別、性格、意思、生活環境等、子に与える影響、同居親の監護養育に与える影響などを考慮して裁判所が判断をすることになります。 話がまとまらないときは、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、審判に移行します。 審判というのは、調停の結果を踏まえて、裁判官が面会交流について決めることをいいます。しかし、審判に対しては当事者どちらかが異議を申し出ることによって裁判官の判断を拒否することができますので、審判で面会交流が決まるということはあまりありません。 そのため、面会交流の調停が不成立に終わった場合には、訴訟に進むことが多いです。訴訟では、面会交流について判決で決定してもらうことができます。判決が確定した場合には、面会交流をさせる側は、相手方に面会交流をすることを義務付けられます。お子様を引き取った側は、理由もなく、別れた相手とお子様との面会を拒否することはできません。 ただし、相手に会うことがお子様の福祉にとって害がある場合は、面接の拒否や制限をすることができます。 理由を説明して面接の拒否を申し入れても相手が納得しないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に面会拒否の調停を申し立てます。また、以前取り決めた面会交流の内容を変更したい場合にも、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停では、調査官がお子様の生活状況や精神状態、意思などを調査して、お子様にとって適正な取り決めができるように話し合いをします。調停でも話し合いがまとまらなければ、審判、訴訟に移行します。これらの流れは、面会交流の調停と同様です。 面会交流の実施については、民間機関でも支援を行っています。そして、その支援方法としては、付き添い、受け渡し又は連絡調整といった種類があります。支援機関としては、公益社団法人家庭問題情報センター(通称「F P I C」))というところがあります。同支援機関を利用するためには、事前相談を受けることやF P I Cが求める内容を面会交流に関する条項を合意書に定めることが必要となっています。そのため、面会交流の実施に不安を感じる場合や第三者機関の利用を考えている場合には、面会交流の合意をする前に事前に相談をすることが必要です。 また、厚生労働省も面会交流支援事業を行っており、条件を満たせば面会当日の子供の引き取り、相手方への引き渡し、交流の場に付き添うといった援助を受けることができます。そのほかにも、各自治体や小規模ながらN P O法人などが面会交流支援事業を行っている例もあるようです。 面会交流は、親権と絡んで、問題になる場合が多いです。例えば、離婚する際に、夫が週に1度面会交流をさせてくれるのであれば親権は母親に譲る、などです。親権が取れない場合でも、面会交流によって、お子様との信頼関係を築いていくことは十分可能です。 ご自身に有利な面会交流を実現するためには、弁護士を入れることが有用です。冷静な話し合いができるだけでなく、交渉のプロとして、相手の弱い部分、こちらの弱い部分を把握したうえで一番良い解決方法を示していきます。 ぜひ一度弁護士にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 「面会交流」に関するQ&A よくあるご質問のうち、面会交流に関するご質問をまとめました。 「面会交流」が争点の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、面会交流が争点であった事例をまとめました。 [myphp file='link-child']
-

養育費
養育費とは、一般的に、父母の離婚後に子どもが生活するために必要な費用のことで、衣食住の費用のほか、教育費や医療費、小遣いなどの適度な娯楽費も含まれます。 離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる側の親(監護親)に引き取らない側の親(非監護親)が養育費を支払います。 離婚をしても親には子どもの扶養義務があります。養育費は離婚の原因や親権者が父母どちらかにかかわらず支払われるべきものです。 ▶ 養育費のシミュレーションはこちら 養育費の支払期間は、第一次的には父母の話合いで決めますが、家庭裁判所の判決や審判の場合には、20歳までが対象となることが一般的です。よくご相談者(養育費を支払う非監護親のほう)から「民法改正で成人年齢が18歳までになったので、養育費も18歳まで払えばいいのではないか。」と相談を受けますが、民法が改正されたからといって、法改正の前後で子どもが社会に出る時期の実態が変わったわけではありませんし、家庭裁判所の実務では変わらず養育費の終期は原則20歳までとされています。 もっとも、いまは大学進学率も高いですし、監護親も子を大学まで行かせたいと思うことは多いので、協議や調停で養育費の定めをする場合には、大学卒業までを終期とすることも実務上はかなり多いです。 養育費の金額に法的な規制があるわけではないので、父母の収入や財産、生活水準などに応じて話合いで決めます。話合いで決める場合には、その取決め方にルールはありません。 もっとも、裁判所や弁護士が介入した場合には、いわゆる「算定表」ないし「算定式」というツールを利用して養育費額を決めることが多いです。 これは、子の数と年齢別に、自分(請求側)の収入を横軸、相手(請求される側)の収入を縦軸とした算定表をもとに、養育費を算出するものです。東京家庭裁判所のホームページに算定表の実物とその使い方が掲載されています。 ここまでは、一般の方でも、弁護士に相談するまでもなく認識されていることが多いようで、弁護士のところに相談に来られる方は、算定表の存在自体は大体皆さんご存知です。 ただし、この算定表は、子の人数、年齢、双方の収入を当てはめるだけで適切な養育費の水準をはじき出してくれるとても便利なものですが、実はその使い方は非常に奥が深いものです。たとえば、この算定表では、養育費については公立学校相当の教育費(~14歳の場合には年額約16万円、15歳~の場合は年額約26万円)しか反映されていませんので、子にそれ以上の教育費がかかっている場合には超過分を請求できる場合があります(「請求できる」と断言していないのは、父母の学歴と比較して過剰な教育ではないかとか、非監護親がその教育を容認しているかなどのファクターが関わってくるためです。)。 養育費は、話合いで決めた期限まで毎月一定額を金融機関に振り込む形で支払うのが一般的です。 もちろん、父母で合意すれば、将来分の養育費をまとめて払ってしまうということも合意は可能です。もっとも、仮に監護親の金銭の使い方に計画性がなく、早いうちに一括で払われた養育費を使い込んでしまったケースをイメージしてください。そのような場合、非監護親としては、「離婚時に一括で養育費を払った以上は、その後の使い込みのことまで責任は持てない、追加の養育費など払わない」、と当然言いたくなるでしょう。なお、ここでは、一括で払い込んだ養育費が、離婚時の合意書等で明確に「(一括払の)養育費」として特定されているとします。しかし、このような場合でも、監護親の使い込みあるいは無計画により、子の生活すら危ぶまれるような場合には、子ども自身から、「扶養料」として生活費の請求がされてこれが認められることがあります。一括で払ってしまうことには、監護親にとってはメリットが多い(毎月の縫う金がきちんとなされているかを都度確認する義務がありませんし、始めに一括で払い込まれた養育費を運用して、結果的に、分割でもらうケースと比べて大きな金額にすることができるかもしれません。)一方、非監護親にとってはリスクがそれなりにあるのです。たとえ非監護親の方のほうの預貯金に余裕があるとしても、一括払の合意をする際は、(非監護親の方は)注意しましょう。 離婚時に子が幼少の場合には養育費の支払は長期間に及ぶので、不払いトラブルも少なくありません。養育費について話合いをしたら、必ず、その内容を文書で残すべきです。そして、文書には、支払期間(終期)、金額、支払方法を明記すべきです。 また、文書化する際は、可能な限り公正証書にすることが望ましいです。公正証書にしておけば、あとあと支払いが滞った場合に裁判を起こさなくても、相手方の給料や財産を差し押さえること(強制執行)ができます。 また、家庭裁判所の手続きを経て離婚する調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合には、公正証書による取決めがなくとも、強制執行により非監護親の預貯金や給料を差し押さえることができます(養育費については、将来分も予め強制執行することができるなど、民事執行法上の特則により制度が手厚くなっています。相手方が勤務先を退職して逃げた場合でも、次の転職先をある程度は追うこともできます。怖いですね。養育費はきちんと払いましょう。)。 離婚後に事情の変化があれば、双方の話合いで養育費の増額・減額をすることができます。話合いがつかない場合には、家庭裁判所に養育費変更(増額or減額)の調停を申し立てます(もちろん話合いを省いて調停をしても構いません。)。調停での話合いにより結論が出なければ「審判」という手続きに自動移行して裁判官による判断がなされますので、相手方が応じなければダメだという類のものではありませんので、相手方が応じないだろうというだけで手続をあきらめるべきではなく、手続き自体は積極的にしていくべきでしょう。 もっとも、審判も裁判の一種ですので、法律あるいは裁判例の基準を満たしていなければ、(相手方が応じない場合には)なかなか養育費の変更は認められません。 養育費の増額が認められる正当な理由としては ・子どもの進学や授業料の値上げによって養育費が増加した ・子どもの病気や怪我で多額の医療費がかかった ・監護者の病気やけが、リストラや会社の倒産で収入が低下した などがあります。 養育費の減額が認められる正当な理由としては、 ・リストラや会社の倒産、事業の失敗、病気、怪我などで、支払う側の収入が低下した ・監護者が就職等で経済的に安定した などがあります。 また、増額・減額を基礎づける正当理由があることに加え、その理由が「元々の養育費額設定時に予想できた事情かどうか」が重視されます。上記の例でいうと、病気が当初から分かっていた場合や、会社の倒産が当初から予想されておりそれが双方の共通認識だった場合には、審判で養育費額の変更は認められづらい方向に働くと思われます。 上記のとおり、養育費額の変更には「正当理由」が必要となるので、「当初合意で取り決めた養育費が算定表より高いまたは低い場合」には、その理由だけで、算定表に基づいた養育費に取り決めなおしたいとの主張は、通りにくいです。ただし、過去の養育費が最初から虚偽や事実の隠蔽により不当に決まり、その養育費を維持することが著しく当事者の公平に反するような場合や、当初の養育費の合意が時期を限定した合意である(と諸々の事情から解釈できる)場合は、算定表による養育費への見直しが認められることもあります。 また若干特殊なケースとしては(「特殊」と言っても実際にはそれなりの頻度で生じます)、監護親が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をするケースがあります。この場合は、再婚相手(養父)が第一次的な扶養義務者になり、実父の扶養義務が後退する結果、養父に子どもの扶養能力がないなどの事情(心情的にはそのような経済状況で子を養子にするなと言いたくなってしまうかもしれませんが)がない限りは、子の養育費は免除されることになります。ただ、この場合でも養父と子の養子縁組により自動的に養育費支払義務が消滅するわけではなく、監護親の方と合意をするか、養育費減額(免除)調停を起こす必要があります。 養育費の終期についても同様です。養育費設定時は子が大学に行くか分からないので終期を20歳と設定していたが、その後、子が大学に進学したため終期を22歳ないしは大学卒業時までというかたちで延ばすことも、調停や審判にて決めることになります。子が将来的に大学に行くかは予想しづらいところなので、このパターンは、一般的に、当初の設定時に予想出来なかったとも言いやすいと思われます。 現在の実務において養育費は一般的に標準算定方式(標準算定方式に基づき簡易早見表を作成したものがいわゆる「算定表」です。)に基づいて大まかな相場が定められております。その為、多くの件はこちらの標準算定方式に基づいて定められていく傾向があります。そうだとすると、養育費問題について弁護士に依頼しても、結局は標準算定方式どおりに決まってしまう以上、弁護士に依頼する必要は無いのでしょうか。 必ずしもそうではありません。あくまで標準算定方式は早期に養育費の金額を確定する為に統計資料等に基づき計算式が定められ、機械的に金額を算出しています。個々の事情によって修正される場合があることまで否定されているわけではなく、きちんとそのような事情を主張立証できれば、標準算定方式と異なる結果となることは決して珍しいことではありません。 このように、養育費問題に熟知した弁護士に依頼し、きちんとご自身の個別の事情を踏まえた主張立証を行うことで、標準算定方式と異なる結果を得られる場合がございます。 ⑴ 自営業者の場合 自営業者の場合も原則として確定申告書記載の「課税される所得金額」を前提に、標準算定方式に基づいて養育費が算定されます。実際、算定表の収入欄には給与所得者の収入と併記される形で自営所得者の収入が記載されています。 もっとも、給与所得者の収入は源泉徴収票等に記載の総収入を単純に参照すれば良いのに対し、自営所得者の場合は必ずしもそうではありません。 「雑損控除」、「寡婦、寡夫控除」、「勤労学生、障碍者控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「青色申告特別控除」といった現実に支給されていないものについては「課税される所得金額」に加算されるべきものです。また、小規模企業共済当化基金控除や寄付金控除も、性質上、養育費の支出に優先すべきものではない為、加算されます。 その他、自営業者の場合、節税等の観点から必要経費が必要以上に計上されている場合が事実上多々あります。そのような経費が本当にその事業を維持する為に必要な経費なのか、単に生活費として支出したものまで経費として計上していないかについて精査すべき場合もございます。 以上のとおり、自営業者の場合、養育費を算定するにあたって前提となる収入の考え方に大きな幅が生じかねない為、事実関係をきちんと精査し、法律上の主張立証をきちんとしているかによって大きく差が出る場合があります。 したがって、当事者が自営業者の場合、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。 ⑵ お子様の教育費が問題となる場合 標準算定方式によって定める養育費は、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費のみが考慮されています。その為、お子様が私立中学校・私立高等学校に進学した場合、塾や習い事を利用している場合、大学等の教育期間に進学した場合の養育費や進学費用については別途検討される必要があります。 もっとも、当然に義務者が全ての教育費について支払い義務を負うわけではあるなせん。従前より義務者が承諾していたかどうかという事情の有無や、義務者の収入・学歴・地位等の一切の事情が考慮されることになります。また、具体的にどの部分の費用が対象となり、どのような方法で加算されるかについては細かい計算を要する場合もあります。 このように、お子様の教育費が問題となる場合、これまでの教育に関する夫婦のやり取りや行動をあらためて整理し、法律上の主張立証をきちんとしているかによって大きく差がでる場合があります。 したがって、お子様の教育費が問題となる場合、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。 ⑶ 夫婦間の子以外の被扶養者がいる場合 認知した子がいる場合や、前妻との子を監護養育している場合等、夫婦間の子以外に被扶養者がいる場合も標準算定方式による計算が複雑化しやすい傾向にあります。 このような場合、義務者が当該被扶養者と実際に監護養育しているのか、単に養育費を支払っているだけなのかによっても検討方法が変わる可能性があります。 したがって、夫婦間の子以外の被扶養者がいる場合、適切な金額を算出するにあたっては弁護士に依頼することで金額が大きく変わることもありますので、一度ご相談ください。 養育費問題で頻繁に問題となり得る事例を中心にご紹介させていただきましたが、ここで記載した事項以外の場合でも標準算定方式を機械的に当てはめるだけでは適切な養育費の金額が定まらないケースは多々あります。弁護士に依頼することで、標準算定方式の幅に捕らわれない結果となる場合もございますので、養育費に悩まれている方は一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 [myphp file='link-footerban'] 「養育費」に関するQ&A よくあるご質問のうち、養育費に関するご質問をまとめました。 「養育費」が条件の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、養育費が争点であった事例をまとめました。 子ども二人の養育費はいくら?養育費の相場について弁護士が解説 養育費はどのようにして計算されるのか ~ 「算定表」「標準算定方式」とは [myphp file='link-child']
-

子どもの連れ去り緊急相談室
妻が子どもを連れて出て行ってしまった、夫の両親が子どもを実家に連れ帰ってしまった、そのようなケースは少なくありません。そのような状況で、あなたがお子様の親権・監護権を取得する為には、一刻も早く、正しいアクションを起こすことが重要です。 まだ離婚が成立していない時点での子どもの連れ去りは、多くの問題を含みます。まずは一度当事務所にご連絡ください。 子ども連れ去りの 対応の流れ 子ども連れ去りに関する 解決事例 子ども連れ去りに関する よくあるQ&A お子様の連れ去り対応は、時間との勝負です。当事務所では、弁護士のスケジュールが空いていれば、即日のご相談も可能です。 0120-77-9014 0120-77-9014 電話受付時間 | 平日 9:00〜18:00 実際に当事務所の弁護士に子どもを連れ去られた経緯、連れ去り以前の監護状況、現在のお子様の状況(わかる範囲で)を詳細にお話ししてください。 子どもを取り返せるかどうかは、同居中の子どもの監護養育を主に父母どちらが担当していたか、子どもが連れ去られた経緯がどのようなものだったかに左右される傾向にあります。 事前にこれらについて簡単に書面(データでも構いません)にまとめていただいているとより正確な見通しがお伝えできるかと思います。ご依頼後、着手金をご入金いただいてからすぐに、当事務所の弁護士が各種準備に着手いたします。 当事務所の弁護士が、お客様を代理して、子の監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判を申し立てます。 また、お子様の引き渡し関係の紛争は、迅速性が求められるため、併せて仮処分を申し立てることも少なくありません。 仮処分を申立てている場合、申立てから1週間から10日ほど後に、審問手続が行われます。審問手続きとは、裁判所にて、裁判官から、仮処分を申し立てた側の方(「申立人」といいます。)が、従前の監護状況や子どもの連れ去りの経緯、その他お子様に関することについて様々な質問をされます。また、相手方の代理人弁護士からも質問を受ける場合もあります。 審問手続の中で話した内容は、裁判官が判断する際に、有利にも不利にもなり得ます。そのため、どのような質問を受けるかについて、事前に弁護士と十分な打合せをする必要があります。場合によっては、当事務所で、当事務所の弁護士とリハーサルを行っていただくことになるかもしれません。 家庭裁判所の調査官が、子どもが現在どのように監護されているのかについて家庭訪問や保育園・幼稚園等への往訪を通じて調査します。また、従前の監護状況について当事者同士に話を聞いた上、同様に保育園、幼稚園での聞き取りを行う場合もあります。 その後、調査官は、調査内容について監護者としてどちらが適切かについての調査報告書を作成します。多くの裁判官の決定は、この報告書の内容に沿った形でなされる為、調査の結果が非常に重要です。 ただし、調査官調査は、裁判所の判断で行われる為、行われない場合があります。 家庭裁判所の調査官とは、裁判所に命じられて、付帯処分等(財産分与、親権者の指定、子の監護に関する処分)に関する事項について調査をする、裁判所の職員です。 無事に「子どもを引き渡せ」という旨の決定が出た場合、最初に相手方に任意の引渡しを求めます。 しかし、相手が必ずしも引き渡しに応じてくれるわけではありません。そもそも、お互いに不信感が募った末に別居をしているケースが多いため、任意での引渡しが容易ではないというのが現状です。 任意の引渡しが困難な場合、強制執行という手段を利用することになります。執行官とともに、子どもが監護されている場所に赴き、子どもを引き取りにいきます。 執行官とは、執行官は、各地方裁判所に所属し、裁判の執行などの事務を行う裁判所の職員です。 当事務所にご依頼いただいた、子ども連れ去りに関する解決事例をご紹介いたします。 1. 子どもの引き渡しを求めた事例 画像はイメージです 依頼者 女性 / 30代 相手方 男性 / 40代 子ども 2人 解決方法 調停、審判 夫が自宅を出て実家に戻る形で別居が開始されました。その際、子どもも一緒に連れ去っていってしまいました。当事者間でメールによる話し合いをしたものの、母は子どもに会うことすらできませんでした。「少しでも早く子どもを取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談にいらっしゃいました。 当事務所の弁護士が、ご依頼をいただいてすぐに、子の引渡し請求と監護者指定の審判の申立て、併せて同仮処分の申し立てを行いました。申立て後、審問手続きを経て、調査官調査が行われ、いずれの子どもについても母が監護権者としてふさわしいという調査報告書が提出されました。その結果、夫に対し、「子どもを妻に引き渡せ」という旨の審判決定が出され、子どもを取り戻すことに成功しました。 審判決定では、別居をする前は依頼者である母が子どもの主に監護しており、特段の問題がなかった認められたこと、子ども自身も母に会いたいという思いを示していたことの2点が子どもの引渡しが認められるための重要な要素となりました。また、夫による連れ去りの態様も、子どもに十分配慮されていないと判断されました。 2. 子どもの引き渡しを求めた事例 画像はイメージです 依頼者 女性 / 40代 相手方 男性 / 50代 子ども 2人 解決方法 調停、審判 夫が妻だけを自宅から追い出しました。その後、夫の両親が子どもを夫の実家に連れて行ってしまいました。当事者間でメールでのやり取りをしたものの、妻は子どもに一度も会えていませんでした。「できる限り早く子どもを取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。 当事務所の弁護士がご依頼をいただいてから速やかに子の引渡し請求、子の監護者指定の審判の申立て、併せて仮処分の申し立てを行いました。申立て後すぐに審問手続が行われ、そのまま調査官調査も行われることとなりました。その結果、いずれの子どもについても依頼者である妻が監護者にふさわしいという報告書が提出されました。 その結果、夫に対して、「妻に子を引き渡せ」という旨の審判決定が出され、無事子どもを取り返すことに成功しました。 審判決定では、夫が妻を自宅から無理やり追い出し、子どもの監護状況を変える際の配慮のないまま夫の両親の自宅に連れて行ってしまったという経緯が、強制的な奪取と認められました。また、子どもが1歳と3歳で極めて幼いことや、その間の母との面会交流が全く実施されておらず、母子関係が完全に断絶されていること、子どもが保育園に通えなくなるなど大きな環境の変化を子どもに強いていることが認められました。 本件では夫も従前から子どもの監護にある程度関与しており、また、現在の夫による監護に特段の問題がないと判断されたものの、それでも妻に子どもを引き渡すべきと判断されました。 3. 子どもの引き渡しを求められた事例 画像はイメージです 依頼者 男性 / 40代 相手方 女性 / 50代 子ども 2人 解決方法 調停、審判 妻が自宅を出て行き、別居が始まりました。その際に、二男のみを連れて行き、長男と長女を夫の自宅に放置していってしまいました。それにもかかわらず、妻が長男及び長女の引渡し請求等の法的手続の申立てを行いました。「妻が勝手に長男と長女を置いて家を出て行ってしまったのに、長男と長女を引き渡すこはできない。」との思いで当事務所にご相談に来られました。 妻側から提出された申立書に対して、当事務所の弁護士が30頁以上の反論書面を提出しました。その後、調査官調査が行われ、夫による監護に特に問題は無いとの意見が提出されました。また、本件では長男が妻に対しあまり良い感情を持っていなかったため、長男の年齢に鑑みると長男の意見を尊重したほうが良い旨の見解も示されていました。 最終的に妻側が子の引き渡し請求等を取り下げ、夫が長男及び長女の監護を継続できることとなりました。 本件では、夫が連れ去り等の強制手段をとることなく、長男と長女の監護を開始したという事情が大きかったと考えられます。また、長男の年齢が思春期に差し掛かる頃だったこともあり、母親との不和があったことも要因の一つです。 他方で長女に関しては、引渡しを認める旨の決定がなされる可能性がありました。もっとも、裁判官は、長女と長男との関係が良好であり、両者を分離させるべきではないという考えから、長男、長女共に父を監護権者とすべき旨の心証を抱かれたのだと思います。 Q1 子どもを連れ去られたときはどのような手段を取ればよいのでしょうか? A1 3つの方法があります。 家庭裁判所に「子の引渡し」を求める調停・審判を申し立てる 「審判前の保全処分」を申し立てる 「人身保護請求」の制度を利用する 1.について 家庭裁判所に「子の引渡し」の調停を申し立てた場合、調停委員を介して、当事者同士で、子どもの意向も尊重した取り決めができるよう話し合います。調停で決着がつかない場合には、自動的に審判に移行します。 2.について 1.に挙げた「子の引渡し」の調停、審判には時間がかかるため、できるだけ早く子供を取り戻したいという場合には、調停、審判の申立てとともに、「審判前の保全処分」を申し立てます。「審判前の保全処分」が認められると、審判を待たずに、「申立人に子供を仮に引き渡せ」という旨の命令が下されます。 3.について 連れ去った親が子どもに暴力を振るうなど緊急を要する場合には、地方裁判所で「人身保護請求」の手続きをとります。原則として弁護士が行うこととなっています。 Q2 子どもの引渡しの審判では、どのような事情が考慮要素となるのでしょうか? A2 簡単に言うと、子どもがどちらの親と生活を共にしたほうが健やかに暮らせるか、という点で、引渡しの有無が決まります。 そのため、従前どちらの親が子どもを主として監護養育していたか、現在の監護状況が子どもの福祉に資するものなのか、子どもを強硬な手段で連れ去る等の行為により子どもを害していないか等の視点が重要になってきます。もちろん、子どもがある程度の年齢になっている場合には、子どもの意思が尊重されることが多いです。 Q3 子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判の決定に相手が従いません。どうすれば良いのでしょうか? A3 強制執行の手続きを踏むことをお勧めします。 強制執行には、子どもを引き渡すまで金銭の支払いを命じ、相手に間接的にプレッシャーを与えていく「間接強制」という手段と、執行官とともに実際子どもを相手の元まで引き取りにいく「直接強制」という手段があります。 もっとも「直接強制」といっても、無理やりお子様たちを連れ去るわけではありません。子どもの年齢等に従って柔軟に対応されることが多く、必ずしも万全な手段ではないことに留意する必要があります。 また、強制執行の手続きを取ることは、お子様たちにとってストレスになる可能性がありますので、その方法も含めて慎重に検討する必要があります。 Q4 人身保護法に基づく子の引渡し請求とは、どのような時に認められるのでしょうか? A4 人身保護請求手続きとは正当な手続きによらないで身体の自由を拘束されているときに被拘禁者または他の誰からも裁判所に自由の回復を求めることができる手続きです。 人身保護請求により子の引渡しが認められる要件は、①子の身体が明らかな違法により拘束されていること、②他に手段がないこと、の2点です。そのため、監護権を有しない側の親による子どもの拘束が行われている場合や、拘束者が子どもに暴力を振るう可能性がある場合等に認められる可能性が高いです。 もっとも、強制執行を行うことができませんので、注意が必要です。要件も厳しいため、基本的には、子の引渡しの調停・審判を利用することが多いです。 [myphp file='link-footerban'] 「親権」に関するQ&A よくあるご質問のうち、親権に関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-child']